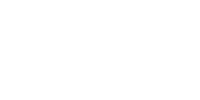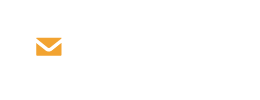事務所ニュース:No.95 2025年4月20日発行
建設アスベスト訴訟の和解解決実現と給付金法改正に向けて
弁護士 森 孝博
昨年12月26日、建設アスベスト訴訟で最大規模の原告を抱える東京1陣訴訟差戻審(東京高裁第24民事部)において、裁判所和解案が提示されました。続く本年1月31日、東京1陣に次ぐ規模の原告を抱える東京2陣訴訟控訴審(東京高裁第17民事部)においても、裁判所和解案が提示されました。
いずれの和解案も、一部の原告について建材メーカーの責任が認められていない等の不十分な点はあるものの、認容率や金額面において高い水準であること、早期解決は原告の強い願いであること等から、原告団は、認定されなかった原告も含めて裁判所和解案を受諾することとし、建材メーカーに対して、真摯な謝罪と和解による一日も早い訴訟解決の実現を迫ることにしました。
東京1陣と2陣の原告数は全国の原告の約3分の1に及び、ここで建材メーカーとの和解が成立すれば、全国的な訴訟解決に結びつけることができます。また、給付金制度への建材メーカーの参加や拠出の大きな前進となることも期待されます。
現在、東京高裁において、裁判所、原告、建材メーカーの三者で和解協議が進められていますが、建材メーカーは、これまで約17年間、賠償責任の存在や賠償額について徹底的に争ってきており、こうした建材メーカーと和解協議の上で合意に至ることは決して容易なことではありません。そのため、原告団を先頭に、力を合わせて、和解成立と給付金制度改正を求める取り組みを強めていますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます(当事務所から小林容子弁護士、山田聡美弁護士、前畑龍弁護士、私が弁護団に参加しています)。
女性差別撤廃条約、日本報告審査、総括所見について
弁護士 千葉 恵子
1 日本は1985年に女性差別撤廃条約を批准しました。
同条約は、あらゆる形態の差別の撤廃を目的としています。条約の実施状況を検討するために女性差別撤廃委員会(CEDAW)が設置されています。
一定の期間ごとに締約国は実施状況について報告を提出し、委員会が政府報告の審査をし総括所見を出すという仕組みになっています。
今回は2024年10月17日、スイスのジュネーブ国連本部で、CEDAWによる条約の日本政府の履行状況についての審議が行われ、同年10月30日付で総括所見が発表されました。
2 今回の総括所見では、前回勧告のあった優生手術被害者への補償金の法律、不同意性交罪への変更と性的同意年齢を16歳に引き上げた改正、DV防止法の改正などの前進面は認めつつも、依然として家父長制の固定観念が根強いという懸念が示され、政治や公的活動への女性の参画推進、教育・研究分野における女性割合の増加、保健分野における現代的避妊法や安全な妊娠中絶へのアクセス確保、婚姻・家族関係における離婚時の財産分与の平等や養育費の確保が勧告されました。さらに選択議定書の批准に対するあらゆる障害を速やかに解消して、個人通報制度を導入するよう勧告し、政府から独立した人権機関を創設するよう強く勧告しました。特に①婚姻後の同姓強制の廃止(民法750条改正)、②一時的措置としての国政選挙の300万円の供託金の削減、③16、17歳の少女に親の同意なく緊急避妊薬を含む安価な避妊法へのアクセスの提供、④中絶に対する配偶者同意の削除については、2年以内にその後の措置を書面で提供するような項目(フォローアップ項目)とされました。
3 私は今回の審査の傍聴のためジュネーブに行ってきました。日本政府の報告の検討をしたり、NGOとしての委員への働きかけ、政府の報告と質問に対する回答を聞き、発表された総括所見の検討などを通じて女性差別を無くしていく、という思いをあらたにしました。
九条の会事務局に加入しました。
弁護士 山田 聡美
ご縁があり、2024年に「九条の会」の事務局に加わりました。
◉ 九条の会
九条の会は、2004年に発足(私が中学生の頃)。当時、日本国憲法改悪を目指す動きや、自衛隊の海外派兵、非核三原則や武器輸出禁止の原則からの逸脱など、軍事優先の政治の動きがありました。
これに対し、平和を求め憲法九条を守りいかすべく、当初大江健三郎さんら9名が呼びかけ人となり発足し、その後、田中優子さんら12名が世話人に。現在、小森陽一さんら6名が事務局となっています。
◉ 最近の「戦争する国づくり」の動き
アメリカが中国との対決姿勢強化の戦略をとる中、日本に対する軍拡要求が強まっています。その中で、岸田政権では、「安保三文書」で、5年で43兆円の防衛費を計上するとして、対GDP比1%の原則を大きく超過。
また、「武器輸出三原則」も「防衛装備移転三原則」とされ、岸田政権でさらに改悪されて武器の輸出が一定認められています。
2013年に制定された「特定秘密保護法」も、岸田政権では、この対象を膨大な経済情報にまで拡大する「経済秘密保護法」を制定しました。
岸田政権は、2024年夏には「9条への自衛隊明記」と「緊急政令」の2つを合わせて改憲発議することを提起し、石破政権もこれを引き継ぐとしています。
◉ 政治を前進する条件が生まれている!署名にご協力ください!
軍拡の動きの一方で2024年秋の総選挙では、自民・公明は過半数を割り、改憲勢力政党も3分の2を割りました。この結果、政治を前進するための条件が生まれています。
武力で平和は作れない、外交こそ政治の役目です。これ以上軍事費に税金を使えば、まさに「軍栄えて民滅びる」社会となってしまいます。
現在取り組まれている「大軍拡反対請願署名」を同封しておりますので、どうぞご協力をお願い致します。
今後も、戦争しない国づくりのためにみなさんと取り組んでいきたいです。
中小企業が行うべきカスハラ対策
弁護士 吉田 悌一郎
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題として注目されています。カスハラとは、顧客や取引先などが、企業や従業員に対して、社会通念上相当な範囲を超える言動を行い、それによって従業員の就業環境が害されることを言います。簡単に言えば、広く顧客などによる嫌がらせ行為を意味します。
カスハラが社会問題化した背景には、コロナ禍における人々のストレスの増大や、「お客様は神様」といった特有の価値観があるとされています。
企業がカスハラを放置すると、対応を余儀なくされた従業員に対する安全配慮義務違反の問題が生じます。そして、近年では、東京都をはじめとする自治体でカスハラ防止条例が制定され、また、労働施策総合推進法の改正で、全企業にカスハラ対策が義務化される予定です。
そこで、中小企業としても、カスハラ対策が必要となります。
具体的には、まず、自社のカスハラ対応方針を明確にすることです。これは、利用規約や自社のHPなどでカスハラへの対応方針を明記します。
さらに、現場でカスハラに対応する社員からの相談を受ける体制の整備、具体的には相談窓口を設置するなどが必要となります。
また、実際にカスハラ被害に遭った際に現場でどのように対応すべきかについてのマニュアルの作成などが必要となります。
カスハラは、正常な企業活動に支障が出るなど、会社にとって大きなリスクになり得るものです。そうしたリスクを防止し、従業員の働きやすい環境を整えるためにも、会社がカスハラ対策に本腰を入れる必要があるでしょう。